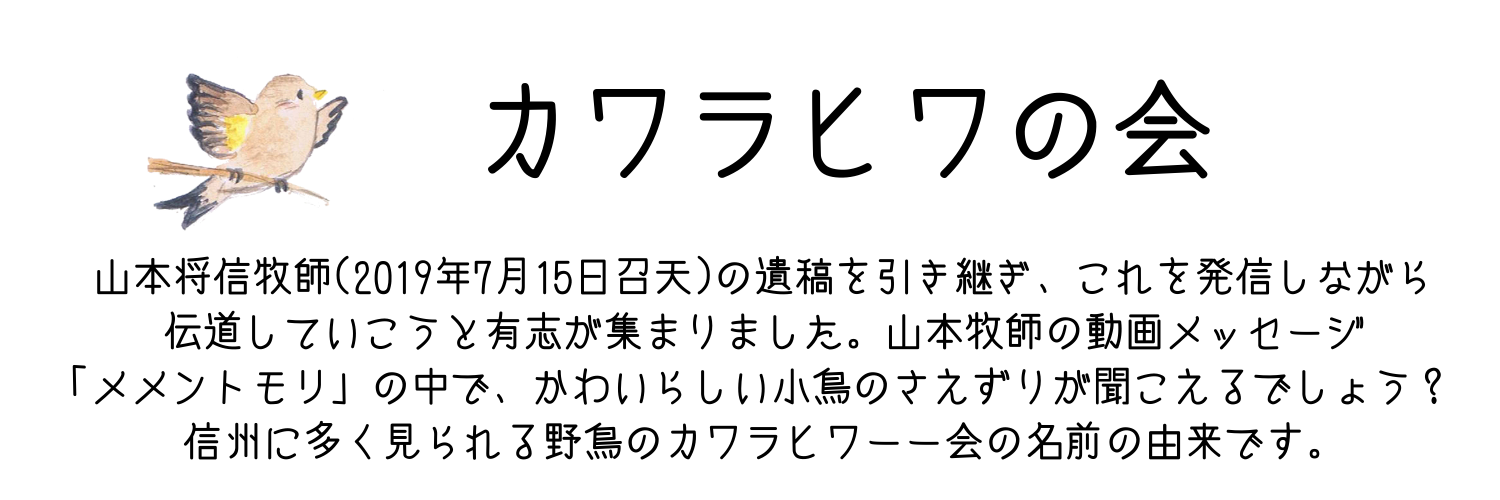この物語は神の国の譬話の結末で語られております。そして弟子たちは神の国のメッセージで聞き、種を携えて「異邦人の地」である「向こう岸」とは私たちにとって福音をイエス・キリストを信じたが故に、懐くようになった志であります。理想と言ってもいいでしょう。私たちが今立っている今日と、志によって見ている明日との間は陸続きの散歩道ではなりません。安全な石橋などないのです。そこには危険な海が横たわっているのであります。「石橋を叩いて渡る」という諺がありますが、叩けるような石橋なのないのです。現状と願望、現実と理想との間には危険な海があって、向こう岸にわたるには小舟で乗り出す勇気が要るのです。
志という「向こう岸」を持たない者にとって、危険な冒険など起こりようがありません。また「向こう岸」という理想や志を眺めているだけでは、人生ではありません。「向こう岸」には漕ぎ出さなければ近づく事さえできないのであります。だがそのためには力は十分であろうか。うまくこの海を越えられるだろうか。考え始めれば切りなく心配ばかりが生じます。
「石橋叩いて渡る」という諺をもじって、第一次南極越冬隊長をされた西堀栄三郎さんが「石橋を叩けば渡れない」という実に面白い本を書いておられます。完全にリスクのない新しい事と言うのはないと彼は書いています。リスクの中には不成功というリスクが入っているわけです。失敗するのは事前調査が足りなかったからだと言われるが、完全にリスクを防止できる調査などあるはずがないというのが西堀さんの考えです。あらかじめ心配した事と実際困った事とはおおよそ違うのが常です。未知の南極越冬を終えて帰ってきて何が一番怖かったかと訊かれたそうです。答えが面白い。「人間です。」次が「すべてが道であると言う事です」と言うのです。
ともあれ「自信」と言う石橋を叩くと、段々心細くなるだけで、結局か渡れなくなります。「自信」と言う石橋をあらかじめ叩いてみて、力強く頼もしい音がした試しはないし、つまり空き缶を叩いた時のような音しかしないものです。無思慮や無謀は慎まなければなりませんが、やはり冒険なくして「向こう側」には近づけないのであります。
自信と言うか信仰や知恵なくして向こう岸に渡れないのも事実です。けれども、それはあらかじめ机上の上で得ることは出来ません。「向こう岸」に向かって漕ぎ出した後で、揺るがされ、脅かされ、そして与えられて育てられるものではないでしょうか。初めから自信などありえないし、仮にあってその自信など頼りになるものではありません。
その消化に12弟子は荒れる海の中で狼狽しています。12弟子の内、少なくとも4人はこのガリラヤ湖の漁師です。この湖を渡る自信がなかった筈はないのです。自分の庭のようなものです。隅から隅まで知っているはずです。
この知っている筈の海は、神の国の志を持って渡る時、全く違った様相を呈し始めたのでした。気軽な日常、従ってつまらない日常も、神の国の志を持つと、厳しい日常、冒険に富んだ日常に姿を変えるのであります。ペテロもヤコブも狼狽します。あらかじめ持っていた自信も信仰も勇気も試されるのであります。試されなければ鍛えられません。鉄は溶鉱炉で精錬され、人間は試練の坩堝で鍛えられるのであります。
この嵐の海の中で、必要な進行も自信も、そして知恵も神は与えられます。机上であらかじめ与えられないのが信仰です。一歩踏み出す勇気です。勇気と言うのは最初の一歩です。極端に言えば最初の一歩だけです。踏み出してしまえば必要なのは勇気ではなく、忍耐とか切り抜ける技量とか落ち着き、あるいは絞り出される知恵です。そして失敗も含めて経験や知恵や練達を育ててくれます。
「向こう岸」は陸続きではありません。漁師であれば、小舟は十分の大きさかも知れません。けれども神の国の志を持つ者には小さ過ぎ、志は重過ぎます。海は荒れ、小舟は揺れ、波が打ち込み、翻弄されます。私たちは試されます。試されて狼狽しない者はありません。
このような危険な状態になれば、しなくてもよい争いがえして始まるものです。こんな会話が聞こえてきます。
「お前さん、それでも漁師か。その漕ぎ方は何だ。」
「てやんで、そんな口叩く暇があったら船から水を搔き出せ。」
「おい、引き返そうや。俺もう嫌だよ。」
「なにいってんだ。今、舟を反転して見ろ。横波くらってひっくりかえっちまうぜ。」
「いわんこっちゃない。夕方になって漕ぎ出すこと自体が無謀だったんだ。」
「誰が、向こう岸にいこうなんて調子のいいこと言ったんだ。」
「今更、何を言い出すんだ。嫌なら来なきゃよかったんだ。
「われわれは無方針、無定見の犠牲者だ。」
「そんな、評論家みたいなこというな。」
「言うなら、漕ぎ出す前に言えよ。」
「大体、イエス先生も先生だ。」
「こんな時に、よくも眠っておられるもんだ。この無神経さに俺耐えられないよ。先生がこんな無神経な人だとは思わなかったよ。全く。」
しかし主イエスは「眠っておられる」のであります。ここが重要なことです。「眠っておられる」とは沈黙しておられるということです。「眠っておられる」とは任せ、委ねておられることを意味します。イエスが眠っておられることは安全であり、安心であることです。弟子たちは「先生、私たちがおぼれ死んでもお構いにならないのですか」と言ってなじります。先生も同じ舟に乗っておられるのです。溺れ死ぬことがあるとしても一緒ではありませんか。イエスは私たちの運命と共におられます。これこそが一番信仰の肝心なことではありませんか。
この湖の突風は突如として吹き、突如としておさまるのが特長なのだそうです。イエスの言葉たまたこの現象と一致したのだと解する人もあります。その詮索がさほど意味があるようにも思えません。また「自然をも支配されるイエス・キリスト」を強調する人もいます。むしろ12弟子、また原始教会から遭わなければなかった迫害、「嵐の中の教会」と歴史の嵐を治められる神の支配がここでは暗示されていると考えられます。私たち、そして「嵐の中の教会」は、韓国で、フィリピンで、東欧で、ラテンアメリカでイエスの信頼して慰められ、嵐に立ち向かう勇気を、嵐を静められる主イエスに励まされているのであります。
主イエスは嵐に向かって「静まれ、黙れ」と叱責されます。パニックに陥っている弟子のパニックでもあります。恐れなければならないのは、恐ろしい嵐よりも、弟子の恐れ自体であります。昂ぶる神経、責任の擦り合い、主イエスへの不信頼、舟の中での騒ぎ、嵐の中でなくとも転覆しかねません。なので主イエスはお叱りになるのです。「どうしてそんなに怖がるのか。どうして信仰がないのか」と。神経が高ぶりパニックに陥っている者にとって、危機感に動揺する落ち着きなさ、深刻な悲壮感に捕らえられている者にとっては神は眠っておられてるように見えるし、思われます。
「主は汝の足を動かさるるをゆるし給わず。汝を守る者はまどろむことなし」(詩編12編)
静まらない嵐はないのです。治まらない混乱もないのです。東京教区総会が20年ぶりに開かれました。感無量のものを覚えます。なおまだあの時、私は30代だったのです。歴史の嵐にもまれたのは東京教区だけでなく、この教会はその代表格の一つでした。礼拝が粉砕されました。会衆が立ち上がると、いわゆる「問題提起者」と自ら呼ぶ若者が座り、会衆が座ると立ち上がって叫ぶのです。要するにわれわれは礼拝ができないのです。世界中を吹き荒れた嵐でもありました。どのような説得も功を奏さないのです。私の理性はマヒし、思考能力は停止状態です。日曜日は容赦なく巡ってきます。そのような騒ぎが一年近く続きました。何が問題だったのか、今でも説明困難です。自らの意志で礼拝を止めまい、警察の力だけは導入すまい。この二つが心に決めた方針でした。それ以外はなにもなかったというのが正直なところです。この二つの方針を貫くために都内4か所に分かれての分散礼拝をし、会堂を明け渡しました。ボクシングジムにぶら下がっているサンドバックのような有様で、ただただ左右が殴られるだけで手の施しようがなかったのです。そのうち静かになりました。論争に勝ったのではありません。殴る方が疲れてどこかに行ってしまいました。嵐は治まってしまったのです。私たちはじっとして今まで通り礼拝をしていただけです。治まらぬ混乱もなく、静まらない嵐はないのです。
「向こう岸」にいたるには、なおまだ多くの試みを経たなければならず、その度に不信仰陥り、主に叱責されねばなりません。叱れることによってもまた私たちは養われるのです。何もしないで失敗しないよりも、失敗し叱られ、そして学んだ方がはるかによいのです。
志なくして安全よりも、志に生きて危険な方がよいのです、「なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。」今一歩月の一歩を保証します。勇気が勇気を生みだし、信仰が信仰を育て、自信が自身の元手となります。今私たちにとって必要なのは「向こう岸」と言う志に向かって、漕ぎ出すことであります。そして試みの中で主に呼ばわることであります。試みによって鍛えることであります。